食事がなぜ一日3回が基本なのか?
本日(5/19)の日経新聞。
「1日3食元気の味方」の見出しで「食事がなぜ一日3回が基本なのか」と解説がされていました。
(以下、記事要約)
日本で朝昼晩と3食とる習慣が広まり始めたのは江戸時代後半。
それまでは、力仕事をする人などを除き2食が一般的だったが、菜種油などを使った明かりの普及や娯楽の広がりなどで一日の活動時間が延び、次第に3食とるようになった。
明治期以降は、人々が時計にあわせて生活するようになり3食が定着。しかし現代は生活習慣が多様になり、一日を2食、1食で済ませるケースも増えている。
1日2食以下にすると、エネルギーを充足したいという脳の作用から1回の食事量が過剰になり、これが習慣化すれば肥満や生活習慣病の原因になる(小林修平・人間総合科学大学特任教授)。
脳は眠っていても活動している。脳を十分に活動させるためには3回の食事が有効(小切間美保・同志社女子大学教授)。
脳に行き渡る栄養源が不足すると脳の委縮を招く。3食をきちんととることで委縮を防げる(白澤卓二・順天堂大学教授)。
食事はホルモンバランスを保つのにも貢献している。人では時間帯により働くホルモンが異なっているのがわかった。これらのホルモンを活性化するのが食事。朝食は一日のスイッチを入れる、昼食は消費エネルギーを補てんする、夕食は体をつくる(蒲池桂子・女子栄養大学教授)。
さらに記事では、食事の質を高めるためのポイントとして、栄養バランス、腹八分目、規則正しい時間、を挙げていて、白澤卓二・順天堂大学教授は「野菜ジュースを毎朝飲むこと」を勧めていました。
やっぱり一日三食。朝食を抜かず、そして夕食は遅くならないように。
仕事の事を考えると難しい場合もあるでしょうが、こういう面からもワーク・ライフバランスを考えたいところです。


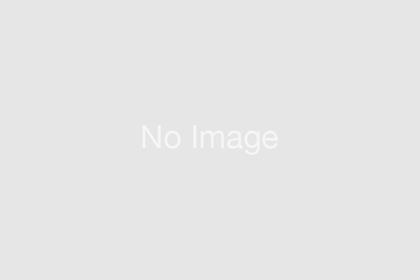





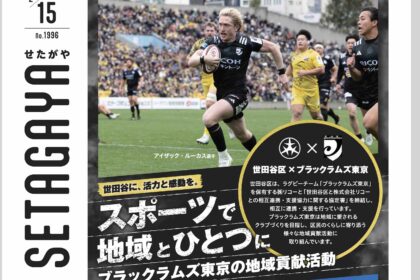
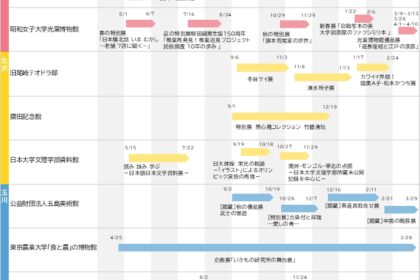
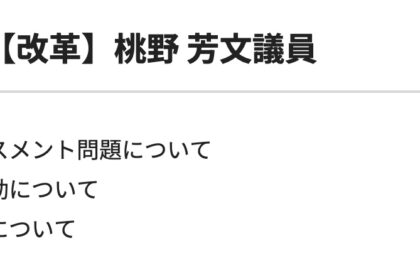
コメントを残す