障がいのある方、又そのご家族の思いについても理解し、その心情に配慮できる社会を。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
今日は「世田谷区聴覚障害者協会 創立70周年記念大会」へ。看板にネコちゃんがいますね。あまりに可愛いので記念撮影しました。福を呼ぶ招き猫ですね。

東京都ろう者協会世田谷支部として結成されたのが昭和29年(1954年)。きこえない人、きこえにくい人が地域社会の中で共に暮らす世田谷となるよう、70年もの長い間、活動を続けてこられました。
この間、ろう者だけでなく、障がいのある方に対する差別的な対応もあったでしょう。かつて手話は「手真似」と言われて蔑まれていた歴史もあると聞きました。
手話はろう者にとって大切な言語。手話を言語とする者に対する偏見、差別、不当な扱いは許されません。世田谷区では令和6年(2024年)4月1日より「手話言語条例」が施行されています。
以下関連ブログ。
手話言語条例を可決。世田谷区議会ではようやく。手話を使う方々にとっても暮らしやすい世田谷区となるよう。取り組みを進めます。
今日は記念講演も行われ、拝聴させていただきました。
記念講演「コーダとは何か」、講師:五十嵐大さん。
五十嵐さんは、映画にもなった「ぼくが生きてる、ふたつの世界」の作者です。
コーダ(CODA)とはChildren Of Deaf Adults、の頭文字をとった言葉。「きこえない、きこえにくい親のもとで育ったきこえる子ども」のことです。
CODAと呼ばれる人達が抱える困難、生きづらさ、葛藤についても多くの方が目を向け理解しなければなりません。
本日の講演の中で五十嵐さんは当事者として大きく4つの点を挙げておられました。
・進学時などの経済的支援
ろう者は職業選択できる範囲が狭くなりがち、又賃金的にも恵まれない仕事に就くことが多い。貧困傾向にある家庭の中でその子どもの進学も限定されがち。アメリカにはコーダを支援するための基金もあるが日本ではコーダを知る人さえ少ない。
・コーダはヤングケアラーでもある。
親に対しては通訳の役割を果たさなければならない。役所で何か手続きが必要なときにも通訳をするが、子どもなので難しい言葉は理解できなこと、うまく伝えられないこともある。本来は社会が担うべき障がい者に対するケアを子どもの時から担わなければいけないことは重荷になっている。
・偏見、差別の問題
五十嵐さんは子どもの頃、ある日近所の子どもから無視されるようになったことがある。あとで分かったことだが親が「障がい者の家庭の子どもと遊んではいけない」と子どもに言い聞かせていた。そうした嫌な目に遭うのは親のせいだと考えてしまっていた。かつては「きこえるお母さんが欲しかった」と酷いことを言ってしまったこともある。又ろう者に対する差別的言動などに触れるたびに自分の親が排除されていることを感じ落ち込み、鬱とした気持ちになる。
・周りの目に対する葛藤
五十嵐さんは、家族の元を離れたいという気持ちが大きくなり、地元を離れて東京に来た。「きこえない親がいる中で頑張ってて偉いね」など周囲から特別視されることがある。労いも負担になる。コーダだからかわいそうと勝手にジャッジされながら生きている。そうしたことから離れたいと思った。
障がいの有無に関係なく誰もが自分らしく生きられる社会をつくらなければなりません。偏見や差別、不当な扱いを無くしていくことはもちろんですが、障がいのある方、又そのご家族の思いについても理解をし、その心情に配慮できる社会をつくっていきたいと思います。


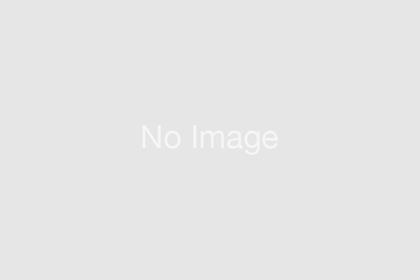








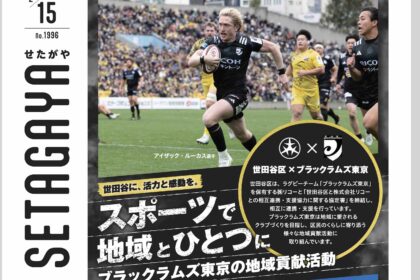
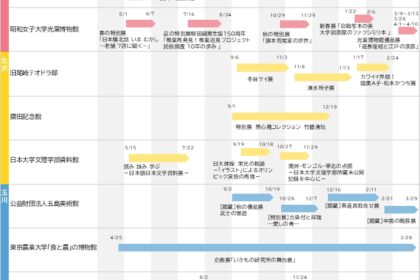
コメントを残す