軽減税率はなぜ導入されてしまうのか。ほとんど(全てのと言っていいかも)の経済学者が反対している政策なのに。
世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
現在開かれている臨時国会でもテーマになっています「消費増税&軽減税率」。
安倍総理大臣は2019年(来年)10月の消費税増税(8%→10%)とともに、その際、食品と新聞は消費税を8%のままに据え置くと公言しています。
軽減税率というか、複数税率といった方がわかりやすいかもしれません。消費税に2パターンの税率をつくりましょうということですね。
まず、この時期に増税していいの?消費が冷え込むのでは?という議論はあるわけですが、もう一つの複数税率導入は、これはもう多くのというか全てのではないかな、経済学者が反対している政策。
当初は財務省も猛反発していました。(麻生財務大臣も複数税率に対して批判的に発言していた)
ツイッターでもリツイートしましたが、創価大学の先生も大反対しています。

詳しくは、こちらを読んで頂けると非常にわかりやすいです。
創価大学 経済学部 准教授の中田大悟さんの「なぜ軽減税率は最悪の選択だったのか」(1)から(4)。
「なぜ軽減税率は最悪の選択だったのか(1)- 資源配分のゆがみ」からぜひご覧ください。
お時間ない方はこちらだけでも。
「なぜ軽減税率は最悪の選択だったのか(4終)- 軽減税率をめぐる誤解や錯誤
簡単にいうと、複数税率導入で国民は確実に「損をする」ということです。
では、なぜここまで経済学者や財務省が反対している政策がどんどんと前に進んでしまうのか。
タイミングよく先日、中田准教授がラジオ出演されていて、非常に興味深いお話を聞くことができました。
まず前提として、この複数税率(軽減税率)の導入を強く主張していたのは公明党です。そして与党とはいえ、決して多くの議席を有しているとはいえない、支持率も他党と比べて決して高いわけではない公明党の主張がなぜこんな形で反映されたのか。
上記の(4)でも少し出てきますが、中田准教授曰く「税の決定過程の曖昧さ」ゆえの問題だと。
・日本の税制の意思決定は非常に特殊。
・税制調査会という組織が二つある。一つは政府税制調査会でもう一つは自民党の税制調査会。
・この二つの組織がけん制しながら緊張感を持ちながら日本の税制を決めてきた。
・結果、責任の所在が非常に曖昧な形で意思決定がなされてきた。
・これまで「どこで決めるのか」が曖昧だったからこそ、安倍政権での官邸主導がそこにすっと入ってきた。
・この場合の官邸主導とは何か。与党の中の公明党が明確に「軽減税率をやるんだ」という意思を持ってきて、それを官邸が丸呑みした。
・誰も納得しなかった軽減税率を公明党が差し込むことができたのも意思決定の曖昧さがあったからこそ。
いやはやという感じですね。
今、地方自治でも国政でも「エビデンスベースト」(evidence based)という言葉が盛んに叫ばれます。つまり「統計データなどの科学的根拠に基づいて政策判断などを行うべし」ということですね。
ところが今、税制という非常に大きなテーマの中で、こうしたことが全く重視されていない現実。官邸主導というのは、それ自体悪いことばかりではありませんが、今回は非常に悪い面が出てきたと言っていいでしょう。




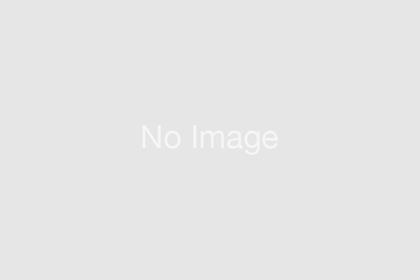



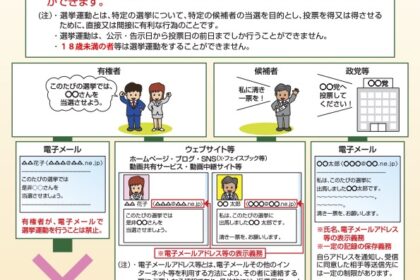

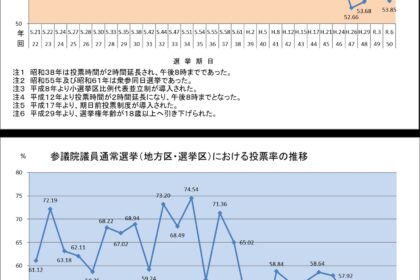
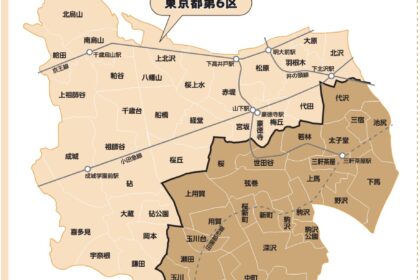
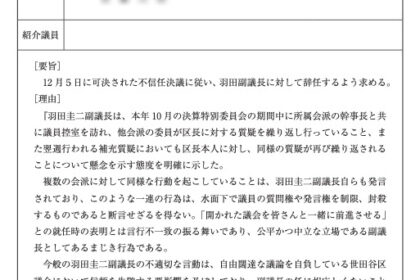
コメントを残す