割り箸
先日、お土産で携帯用の袋に包まれた美しいお箸をいただきました。
和風の洒落たデザインの袋でしたので、持ち歩きたくなりました。
確かに、自分の箸を持ち歩く方いらっしゃいますよね。
外食店等でも「環境に配慮して割り箸は使用しておりません」等の張り紙があったり、スーパーで惣菜を買っても「割り箸いりません」って言う人が増えたり。
最近、割り箸がちょっと悪者みたい。
そもそも日本人はいつ頃から割り箸を使いはじめたのでしょうか。
江戸のくらし研究家、寺島孝一さんによると、18世紀後半に作られた川柳に登場するのが割り箸の最初の記録だそうです。
当時は裂き箸と呼ばれていて、江戸、京都、大阪の大都市で、主に遊郭や茶屋で使われはじめ、徐々に中級の店、大衆的な店に広がっていったとされています。
当初は割り箸を使って食事をするのは、都市の高級店で流行するおしゃれなスタイルだったのかもしれません。
割り箸は、食事の際に割り裂いて使用することから、箸が未使用で清潔であることを明らかにします。これをおもてなしの心とする考えから使われ始めたようです。
以降、簡便、安価であること、洗浄の手間がはぶけることなどから広く普及していきました。
ただし、この習慣が庶民にまで広がるのは明治以降。
割り箸が機械で大量生産される時代まで待たなければなりません。
19世紀には割り箸をみて、「一本の箸で、さてどうやって食事をしようか」と悩んだり割り箸を二膳使って食事をしてしまった」などの事があったようです。
時代は下って現代。
割り箸の使用は1960年代以降、外食市場の拡大とともに増え続け、2000年には国民一人あたり年間200膳程度が使用されています。
しかし、エコブームで「マイ箸」を持ち歩く人が増え、外食市場の縮小傾向、外食店でも割り箸不使用の店が増えたこと等を要因として、割り箸の使用量は、近年漸減傾向にあるようです。
一方、「割り箸の生産が森林破壊につながっている」という主張に対して「割り箸は低利用材や間伐材から作られおり森林再生サイクルの為に重要」という主張もあり、論争は続いています。
江戸時代、使用済みの割り箸は丸箸に削りなおし再利用されていたそうです。
今で言うリサイクルですね。



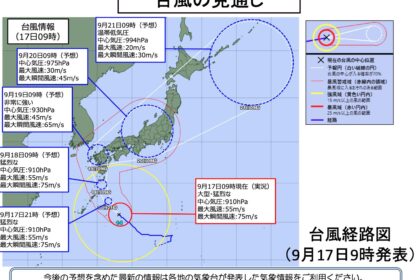
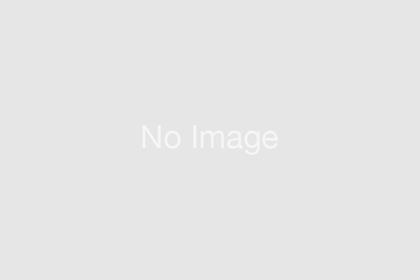









コメントを残す