終末期の高齢者が本人の意思で「穏やかに逝きたい」と思っていても、家族が119番通報し救急隊が到着する、その時に。
世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
今朝のニュースで気になったのが以下の新聞記事。
【救急現場の蘇生中止ルール明確化 学会が指針】(リンクは中日新聞のサイト)
・各地の消防本部や救急隊員、医師らでつくる日本臨床救急医学会が、終末期で心肺が停止した患者に対し、救急隊が蘇生措置を実施するかどうか判断する際の指針を公表した
・本人が蘇生を望まない意思を事前に書面で残し、かかりつけ医らの指示が確認できた場合は、救急隊に蘇生中止を認める
・家族が蘇生を希望したり、事故や外傷などが原因と疑われたりする場合は、患者の意思にかかわらず蘇生を続ける必要がある
との内容です。
高齢の家族が最期の時を家で迎える、又は施設で迎えるとなった時、心構えも含めて本人、家族はどういう準備をするべきか。これまで、そういうことを深く考えたことなかったな。自分も当事者になりうる一人なのに。
病院に入院している状況なら、お医者さんも看護婦さんも周りにいて、目の前で起きていることにどのように対応すべきかというのは、先ずは病院側で判断してくれるでしょう。
でも、自宅だったらどうか。
終末期の高齢者が、本人の意思で「穏やかに逝きたい」と思っていても、家族が119番通報し、救急隊が到着するという例もあるでしょう。
そうなると、救急隊員は任務として、心肺が停止していても、(本人の意思の如何に関わらず)人工呼吸や心臓マッサージなどの蘇生措置を行うことになります。
それを是とするか否か。
自分は蘇生措置を望むのか。桃野ももう少し年を重ねたら、これは近親者にしっかりと伝え、また書面に残しておかないといけないなと思いました。
日本臨床救急医学会は「終末期の高齢者の場合で、本人が蘇生を望まないのであれば、119番通報をしないというのが理想」との考えも示しているよう。
ことは人の生死に関わることです。
そうした意識を社会全体で共有できるのかどうか、これは時間をかけて答えが出されていくのでしょう。その前提として、医療の現場からこうした考え方が示され、報道されることは大きな意義のあることだと思います。
■2017.05.08 東京新聞



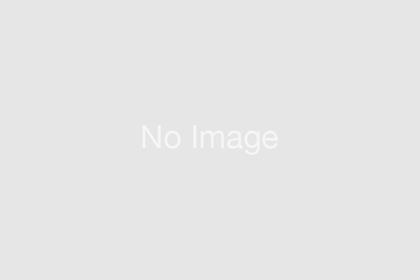

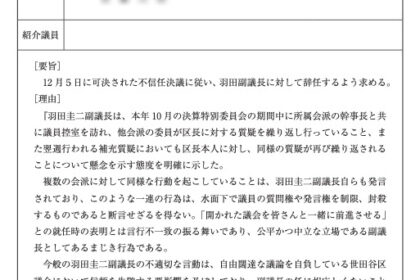





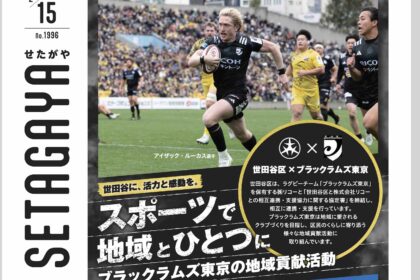
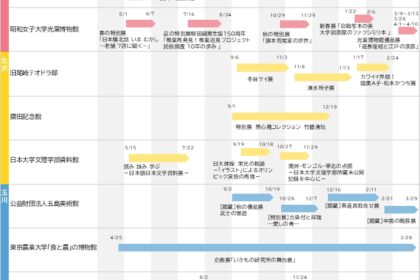
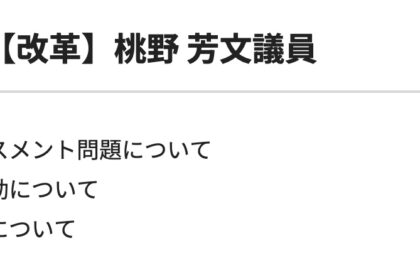
コメントを残す